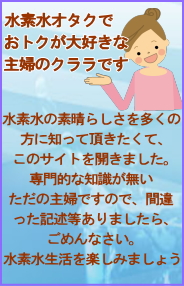活性水素水とは?

本ページはプロモーションが含まれています
活性水素水とは、「活性水素」が溶けているとという水の呼び名です。
健康関連商品の販売のために使われている擬似科学・造語であり、科学的な用語ではありません。
この「活性水素」は、原子「H」をさします。
1997年、九州大学白畑實隆教授の研究から「水素水」という言葉が生まれました。
白畑教授は、「体内の活性酸素の解消には活性水素が有効である」との自説を唱え、「水素原子を含んだ水の健康維持効果」を広めていきました。
この説の活性水素とは水素原子(H)のことを指し、「水素ラジカル」と表現されることもあります。
活性水素水を発生させる手法は、「マグネシウムなどの金属を用いる方法」と「電解による方法」が用いられています。
活性水素「水素ラジカル」は発生しても瞬間的に消えてしまうため、活性水素を安定溶存させた「活性水素水」というものは本来存在しえないとも言われています。
「活性水素水」は水素ガス・水素分子(H2)を溶解させた「水素水」とは区別されます。
『通常分子状で存在する水素(H2)ですが、原子状の水素(H)はより酸素との反応力が強い(酸化還元力≒抗酸化力が強い)とし、これを活性水素と呼ぶ人もいます。
水素水の還元電位の低さを原子状の水素の存在で説明する活性水素説にのっとった商品もすでに販売されていますが、原子状水素の存在についてはまだ科学的な証拠が不十分であるとされ、研究者の中には生体内での活性水素(原子状水素)の存在を否定する説もあります。(参考:日本医科大の細胞生物学分野・太田成男教授の研究室)』
このサイトで考えている水素とは、H2であり、水素水とは水素分子が溶解している水を指しています。活性水素水ではありません
活性水素水商法
活性水素水が活性酸素を消滅させるという事から、健康に良い効能があるということで、「活性水素水を製造するとする装置」が販売されていました。
それらの装置の宣伝では「活性水素水」で、料理がおいししくなる、柔らかくなる、肌がきれいにになる、、「魔法の水」などとされていました。
「アルカリイオン水の生成機」の宣伝トークとして、あるメーカーが使い始めた「活性水素水」という言葉が、メディアに現れたのが最初のことのようです。
大手メーカーからも、家庭飲料用電解水生成装置はいろいろと発売されています。
科学的学術的根拠の上に販売されているものがある中に、インチキ商品も少なからずありました。
水素分子(H2)を溶解した「水素水」は、活性水素水とは学術的な面を含め区別されます。
電解分解水生成器は、1958年から作られていて、長い歴史があります。白畑教授の時に一部メーカーが「活性水素水生成器」と謳ったりしていましたが、その流れは現在も続いており、整水器の大半のシェアを持っていて、2007年に登場した太田成男教授の水素分子説の水素水とは、全く区別されるものです。
大きく分けるなら、太田成男説にのっとった水素水は、中性です。
アルカリイオン整水器、電解還元水素水生成器の水素水はアルカリ生です。
「マイナス水素イオン」「活性水素」と書かれている商品は、場合によっては疑ってみた方が良いです。
太田教授 対 白畑教授 | 分子 対 原子
1997年九州大学白畑實隆教授は、「体内の活性酸素の解消には活性水素が有効である」との自説を唱え、「水素原子を含んだ水の健康維持効果」を広めていきました。
この時、この水素を多く含んだ水を「水素豊富水」「活性水素水」と称したことから「水素水」という言葉が使われるようになりました。
太田成男教授は、分子状の水素を含んだ水を水素水としています。
太田教授と白畑教授の違いは、分子説か原子説(原子イオン)です。
白畑教授の「あらゆる病気を水素が治す!驚きの効果」の動画を
ご紹介します。
両教授が「水素」「活性酸素」という言葉を使いながらも、その違いがはっきりわかりますね。
関連ページ
- 水素水の濃度について
- 水素水は飲む時点での溶存水素量がいくらであるかが、とても大切です
- 「ナノバブル」とは
- 新しい技術「ナノバブル」によって、水素水の概念が変わります。
- 酸化還元電位とは
- 水素水によく表示されている「酸化還元電位とは」何を意味するのでしょうか?
- アルカリイオン水と水素水の違い
- アルカリイオン整水器とは
- 日本分子状水素医学生物学会について
- 日本分子状水素医学生物学会が日本分子状水素医学シンポジウムから移行されて発足しました。水素水に対する見解、賛助会員について説明しています。
- 最新の水素水についての見解
- 国立健康・栄養研究所のデータベースで、水素水について定義されました。人への有効性について信頼できる十分な情報が見当たらないという見解ですが、その意味について解説しています。
- 海外の水素水の状況
- 水素水の研究はアメリカ・中国をはじめとする世界の研究機関・大学・政府機関などで実施され、随時論文発表が行われています。水素水のISO認証を目指す動きもあります。